東京2020レガシーと日本スポーツ界の未来 ~ 日本スポーツ協会・泉正文副会長インタビュー
1964年 東京オリンピック以来の国内での夏季大会開催となった東京2020大会。
新型コロナウイルス感染症の影響で、一年の延期や無観客での競技開催など、前例の無い大会運営となる中、多くのアスリート達が夢や感動を与えてくれました。
東京2020から1年の節目を迎えた今、Journal-ONEはスペシャル対談を企画。
Journal-ONE編集長が、日本スポーツ協会の泉正文副会長にお話しを伺いました。
聞き手:(Journal-ONE編集長)
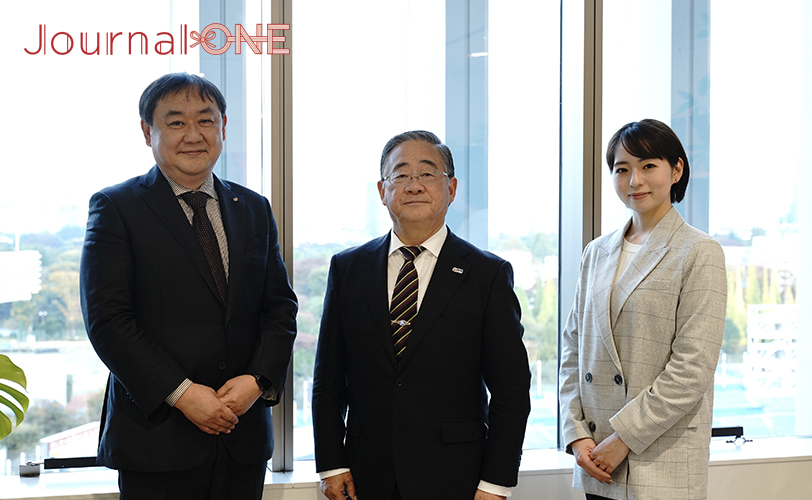
東京2020を振り返って
世界の注目を浴びる大きなイベントである東京2020が、コロナ禍という全く特種な状況下で開かれて、しかも結果として国民からも相当高い支持を受けたと思っております。
特別な意義のあった大会ではないかと思っていますが、JSPOの立場として今振返ったときに最初に思うことはどんなことでしょうか。-
まずは1年経つのは早いなぁという印象ですね。
コロナ禍での大会開催をめぐっては大変厳しい声を含め、たくさんの方からさまざまな意見がありました。その点は真摯に受け止めなくてはいけないと思っています。ただ、オリンピック、パラリンピックともに無観客という形でしたが開催でき、日本が世界に対する約束を果たせたという意味では、一人のスポーツ人としてやって良かったなと感じています。また、共同通信社のアンケート調査で、「開催して良かった」と約7割の方が回答したことには誇らしい気持ちを持っています。
しかしながら、無観客になり、アスリートの皆さんに気の毒な思いをさせてしまったと感じています。また、子どもたちが世界のトップアスリートを生で観戦する機会を得られなかったこと、スポーツ少年団の子どもたちが選手をエスコートして試合会場に入る「エスコートキッズ」のイベントが中止になったことは本当に残念でした。

昨今報道で取り沙汰されている「贈収賄疑惑」については、組織委員会の理事を務めていましたので、大きな責任を感じている次第です。すでに取組は始まっていますが、検証をしっかり行い、国際大会開催時の透明性と公平性を担保する改革が必要だと考えています。

全くその通りです。
東京2020レガシーを引き継いで
レガシーには、ハードとソフトの双方があると思っています。
まず、ハード面では、東京オリンピックの開催決定を契機に、東京都が神宮外苑地域にスポーツ施設を集積させるスポーツクラスター整備構想を進め、新国立競技場の建設はもちろん、競技施設整備に伴って生じた空地を活用して、私たちスポーツ関係団体の拠点(JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE)も新たに整備されました。

そうです。秩父宮ラグビー場や、明治神宮球場などもこれから建て替えが始まりますので、この界隈が日本のスポーツのメッカとして賑わうことを期待しています。
それから、ソフト面のレガシーとしては、「多様性と調和」という概念が非常に進んだのではないかと実感しています。多様性を尊重する意識を引き続き浸透させていく取り組みを今後も行っていくことが必要だと思っています。
また、多くの皆さんにボランティアとして活動いただきました。大会後も様々なスポーツ大会でボランティアの皆さんが活躍されています。これも大きなレガシーです。

そのほかにも、スケートボードなどのアーバンスポーツや、デジタルを活用した大会運営、コロナ禍での競技運営など、これまでなかったことを取り入れたこともレガシーのひとつだと感じています。
一方、コロナ禍で「オリンピックだけが特別なのか」といった議論が国民世論を二分してしまう場面もあったことは負の遺産だと思っています。この点は、今後のJSPOの活動においても意識して取り組まなければならないと考えています。
それも一理あるかとは思いますが、オリンピック・パラリンピック開催の当初の目的があいまいになり、開催目的を周知できなかったことが原因なのではないかと思っています。










