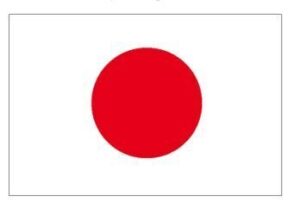突然訪れたチャレンジの機会
人間、幾つになっても新しいことにチャレンジしたい!でも、年を重ねるごとにその意欲やきっかけが少なくなってきます。「ご縁とタイミングってあるんだなぁ。」とつぶやきながら、柔道衣に袖を通した稽古初日の朝7時前。
日本のお家芸として、先のオリンピック・東京大会でも金メダル9個を含む12個のメダルを獲得。コロナ禍で沈んでいた私たちに大きな感動と夢を与えてくれた柔道ですが、まさか自分が柔道の聖地・講道館で柔道をすることになろうとは思ってもみませんでした。
今回の企画はある会議で、「矢澤さん。今度、講道館で未経験でも参加いただける朝稽古を始めることになったんですよ。是非、取材に来て下さい。」と講道館 国際部の仮屋 力さんに教えていただいたことに始まりました。
同席されていた、講道館第5代館長の上村 春樹さんからも、「是非、(取材に)来て下さい。」とお誘いをいただき、直ぐに講道館ホームページから申し込みを完了!新たなチャレンジを得た何とも言えない高揚感と共に、「本当にできるんだろうか?」と不安も感じながら東京・春日にある、講道館国際柔道センターの4階にやって来たのです。
世界中の柔道家たちの憧れの地に立つ!
“本家” “聖地” “発祥の地”と聞いて、皆さんはどんなことを想像しますか?
自分の仕事や趣味、食べ物などにもそのルーツがあり、そのルーツを訪れること自体が観光となっているケースも多く見かけられます。有名アーティストの生家、人気アニメのシーンで出てきた土地巡りなど、誰もが一度は何かしらのルーツへ足を運んだことがあるのではないでしょうか。
柔道の “発祥の地” 講道館も、日本の柔道家はもちろん、世界207カ国の柔道家の憧れの場所。特に、数多のオリンピック選手が修行した、7階にある “大道場” で修行するために1年に何回も日本に足を運んでくる海外の柔道家も多くいる “柔道の聖地” です。海外からの修行者の中には大道場に立てることに感動して涙を流される方もいらっしゃるのだとか。そこで素人が柔道をするなんて・・・ 野球でいえば “素人がいきなり甲子園のマウンドから投げる”、演劇でいえば “素人がいきなりブロードウェイの舞台で演じる” といったところです。
しかし、ここ講道館国際柔道センターは誰でも入ることの出来る、非常に寛容な施設なんです。詳しくは、Journal-ONEで紹介した『世界中から人々が集まる “柔道の聖地” ~ 講道館(東京)』の記事を読んでいただければ、その理由が分かります。
緊張感と高揚感が入り交じる初日の集合
大道場に集まった、朝稽古の参加者はおよそ80名。この後7日間、色々な参加者が出たり入ったりしていましたが、延べ参加者数は約600人に及んだという “朝稽古”。毎朝7時から8時30分に行われたこの取り組みは、「学生の方や会社勤めの方でも始業前に参加ができますので、ジョギング感覚で汗を流して爽快な1日の始まりにしてもらえれば。(仮屋さん)」との思い通り、スーツを着た方も多く参加されていました。
大道場に足を踏み入れた初日、「オリンピックの開会式のような国際色豊かな人たちが集まったなぁ」と思うほど様々な国の方が参加しています。最近、街には多くのインバウンド(訪日外国人観光客)の皆さんを見かけるようになり、以前よりも世界が身近に感じるようになってきた日本ですが、ここ講道館は、更に国際色豊かです。
しかも、小学生の子どもからご年配の方まで年齢層も幅広い!女性の柔道家も3割くらいはいるでしょうか。それぞれが、朝稽古を前にストレッチなどの準備をしています。
「おはようございます。いよいよ始まりますね。頑張って!」と笑顔で声を掛けていただいたのは上村館長です。ご挨拶をしていると、次々と外国人柔道家が集まってきて、上村館長に挨拶をしています。
稽古前に記念撮影をお願いする柔道家もいて(この後、7日間毎日記念撮影を求められていました)、やはりオリンピック・モントリオール大会の金メダリスト、上村館長の人気は絶大です。
私が体験した第1回講道館朝稽古は、体験、技、形、乱取と経験や気分に合わせた4つのコースに分かれていて、“都合の良い日だけ参加OK” “途中からの参加、コースの移動、退出OK” という、個々の都合にも配慮されたプログラム。参加費は無料で、私のような初心者には柔道衣も貸していただけるんです!稽古後はシャワーを浴びることもできますので、会社の出勤時間前にその日の体調と相談しながら、無理なく体験できる素晴らしい仕組みとなっています。
エジプトから工場実習で来日しているというムスタバさんは、「柔道は少しだけエジプトで体験したことはあるけど、日本にいる間にどうしても聖地・講道館で柔道を習いたかったんだ!」と興奮気味に話します。