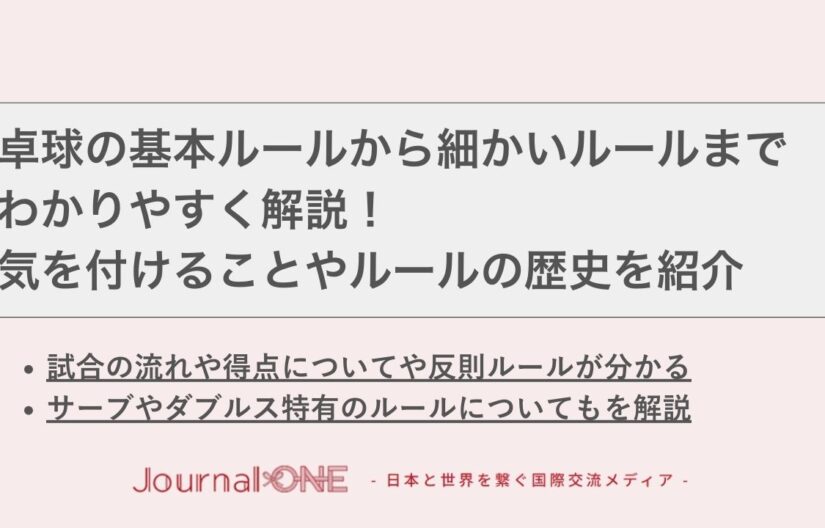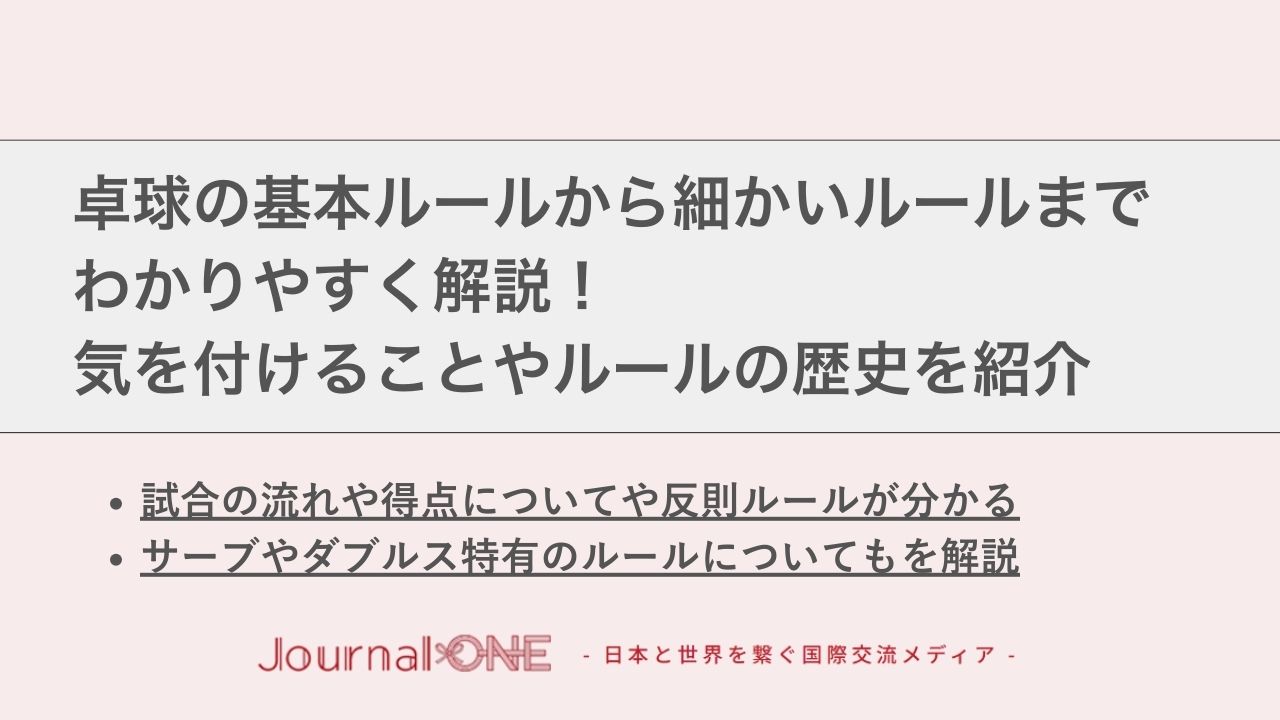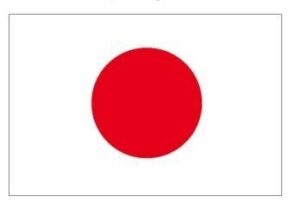サーブを打った後に自分のコートに1回バウンドさせ、相手のコートにもう1回バウンドさせることが大切です。
卓球のダブルス特有のルール

卓球はシングルス以外にも、ダブルスやミックスダブルスとう種目があります。ダブルスには特有の動作やルールなどがあり、卓球初心者にはわかりにくい部分が多いです。
本章では卓球のダブルスのルールを紹介するので、ダブルスをまだ体験したことがない人は参考にしてみてください。
サーブを対角に打つ
ダブルスにおけるサーブは、対角線上で半面に打つことが基本です。たとえばサーバーが右利きだった場合、フォアサイド側から対角線上、すなわち右側でなければサーブを打てません。
2人が交互に打つ
卓球のダブルスでは、2人が交互に打たなければいけません。同じ選手が連続でレシーブをした場合は、ルール違反と見なされて相手の得点になってしまいます。
卓球のルール変更の歴史

卓球は競技の公平性を保つために、試合や用具の規定などのさまざまなルール変更が行なわれてきました。
本章では卓球のルール変更について、選手に大きく影響を与えたものを紹介します。卓球のルール変更の歴史を知りたい人は、ぜひ参考にしてみください。
2000年 ボールの大きさが変更
1999年までは卓球ボールが直径3.8cm・重量2.5gでしたが、2000年からは直径4cm・重量2.7gに変更されています。ボールを少し大きくすることで空気抵抗がかかるようになり、さらにスピードが遅くなってラリーが続きやすくなりました。
現在の卓球ボールに変わると、プレーヤーと観客ともに面白みを感じられるようになり、以前より人気が高くなったそうです。
2001年 勝敗が11点制に
2000年までの卓球は1セット21点・3セット先取というルールでしたが、2001年からは1セット11点・5ゲーム先取に変更されます。ルール変更したことで逆転のチャンスが増え、より白熱的な試合ができるようになりました。
サーブも5本交代から2本交代に変更され、サーブのみで得点が多く入ることも減ってきています。
2014年 プラスチックボールへ変更
2013年までの卓球ボールはセルロイド製でしたが、2014年からはプラスチック製に変更されています。理由はセルロイドの卓球ボールはつなぎ目から割れやすく、さらに燃えやすくて製造や輸送が大変だったためです。
プラスチック製のボールは割れにくく、回転しづらくラリーが続きやすい利点があります。
「卓球のルール」についてよくある質問

卓球のルールはとても細かく、まだ卓球を始めたばかりの人は覚えるのが大変です。
そこで本章では、卓球に関するQ&A で代表的なものを紹介します。
卓球の試合で白いユニフォームを着てはいけない理由を知りたいです
卓球では白いボールを使う場合がほとんどで、白いユニフォームを着てしまうとボールが視認しづらくなってしまいます。公式試合で着るユニフォームは、ボールの色と明らかに違う色でなければいけません。
試合によってはオレンジのボールが使われることもあり、その場合はオレンジ系統のユニフォームを着てはいけないとされています。
卓球に暗黙のルールはありますか?
卓球の国際大会では、相手チームが0点の状態で勝たないことが暗黙のルールです。自分のチームが相手のチームを完封し、面子を潰さないようにという配慮をもとに、約15年前に中国で定められました。
仮に試合が10-0だった場合は、0点のチームにわざと1点をあげなければいけません。このルールに対し、世間からは「ただの茶番だ」という意見が多く挙がっているそうです。
卓球のルール違反を一覧で説明してほしいです
卓球のルールは試合中のものだけでなく、サーブや道具などにも定められています。まずは試合のルールから一緒に確認してみましょう。
- 試合中に大声を上げる
- ラケットを投げる
- 手首より先以外(腕や肩など)で打つ
- ボールの2度打ち
- フリーハンドで卓球台を触る
- ネットに触れる
- 卓球台を動かす
続いて、卓球のサーブにおけるルール違反を紹介します。
- 台の上でサーブをする
- 相手が構える前にサーブを出す
- ボールをトスするときの高さが16cm未満
- ボールを握ったままトスをする
- ボールを垂直に投げられない
- ボールから手を離してすぐに打つ
- ボールがラケットに当たる瞬間を隠す
卓球の道具にもルールがあり、しっかりと手入れしておくことが大切です。
- ラバーに剥がれや傷などがある
- 両面に同じ色のラバーを貼る
以上のルール違反をしてしまうと、試合中にレッドカードやイエローカードが出されてしまいます。場合によってはペナルティが科されてしまうので、ルールを守りながら卓球を楽しむようにしてください。
ラケットのラバーの色にルールはありますか?
卓球ラケットのラバーはITTFまたはJ.T.T.A.A.のマークが入っており、必ず片面に黒のラバーを貼らなければいけません。現在はピンクや水色などのラバーが展開され、2022年からは赤以外のカラーラバーが使えるようになりました。