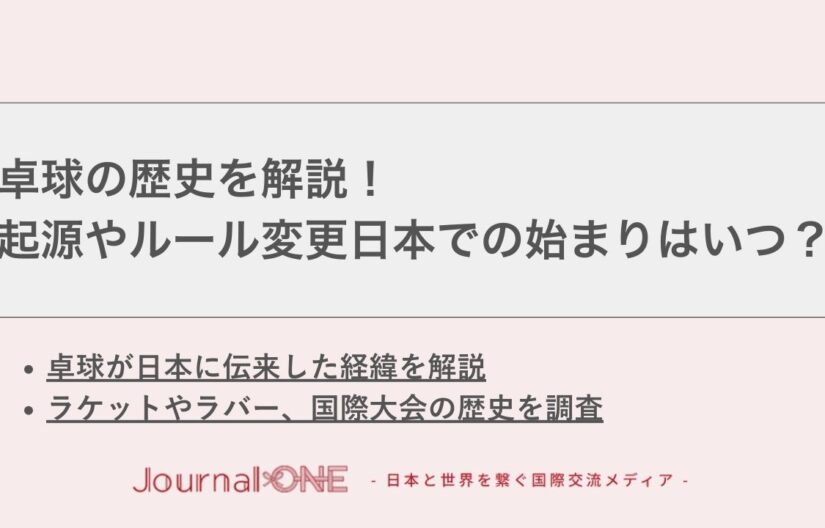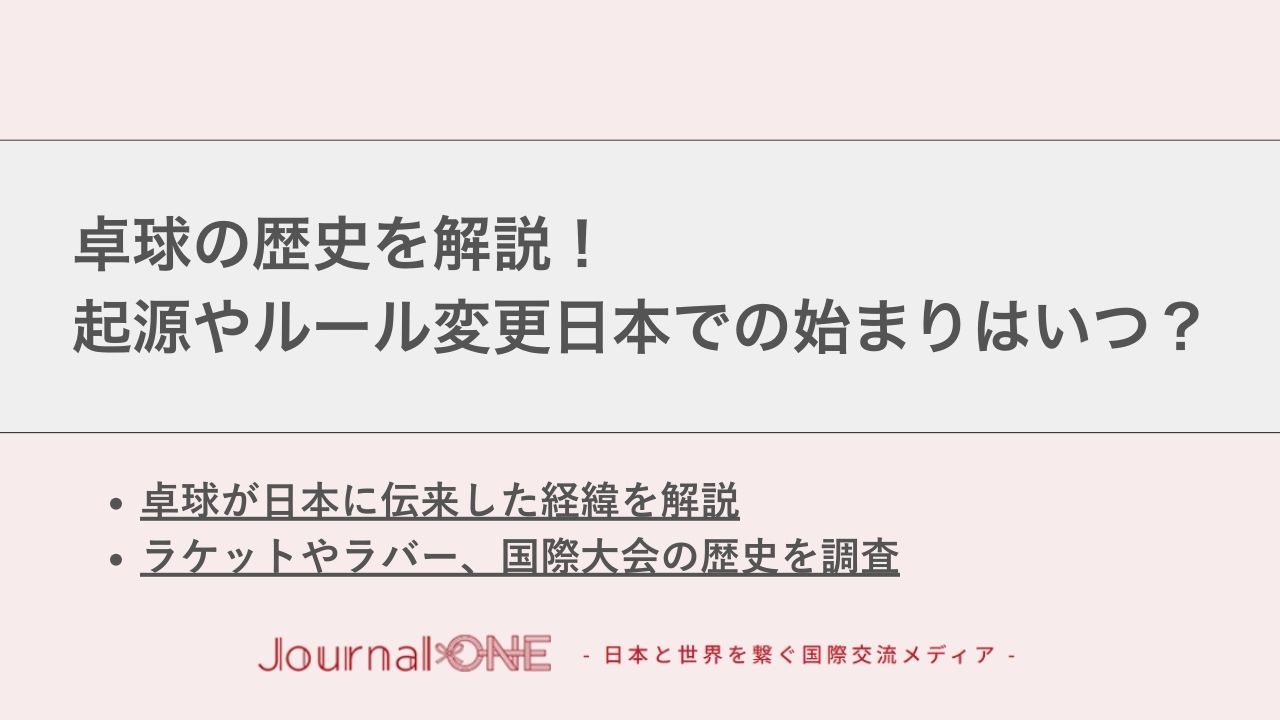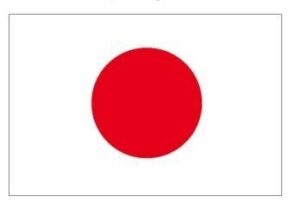卓球のラケット・ラバーの歴史

最初から現在のラケットやラバーだった訳ではなく、初期はテニスの代替品のようなものでした。現在の卓球スタイルになるまでに、ラケットやラバーも様々な移り変わりをしています。
ここでは、ラケットとラバーの歴史を掘り下げてみましょう。
ラケットの歴史
19世紀の頃に使用していたのは、バトルドアラケットという、バトミントンのようなラケットでした。ラバーはなく、紙やすりや革が貼られていました。徐々にラケットの柄は短くなり、今のようなスタイルになりました。
ラバーの歴史
1902年、当時イギリスで卓球界で無名の男性が、突然勝ち進んで優勝をしたことがありました。その男性のラケットを確認すると、薄いゴムの板が貼り付けられていたのが、ラバーの起源と言われています。
男性は、薬局に行った際に薬を計る天秤皿に使われたゴムを見て思いついたそう。皿に使われているゴムは、粒状の突起があり、これが球に回転を掛けられるのではと考え付いたのが起源と言われています。
卓球のルールの歴史

長い歴史の中、卓球ではこれまでに複数のルールが変更されています。例えば、フィンガースピンサービス。これはサービス時にフリーハンドを使用、ボールに強力な回転をかけるという技です。
フィンガースピンサービスは強力な威力を発揮する一方、レシーブミスが連発したり、ラリーが継続しないデメリットがありました。卓球の面白さに欠けるとして、後にフィンガースピンサービスは使用禁止となります。
他にも、ネットの高さを引き下げたり、試合時間を極端に長引かせないための促進ルールを導入しました。
卓球のオリンピックでの歴史

1988年にオリンピック競技となった卓球は、現在までに多くのスターを誕生させました。ここで1度、オリンピックで開催された卓球の歴史をチェックしてみましょう。
- 1988年 ソウルオリンピック
- 1992年 バルセロナオリンピック
- 1996年 アトランタオリンピック
- 2000年 シドニーオリンピック
- 2004年 アテネオリンピック
- 2008年 北京オリンピック
- 2012年 ロンドンオリンピック
- 2016年 リオデジャネイロオリンピック
- 2020年 東京オリンピック
- 2024年 パリオリンピック
卓球の歴史で「中国」が出てくるのはなぜ?

中国が卓球を国技とし、力を入れているからです。
アヘン戦争で欧米に負けた中国人は、自分達に自信をつけるために、卓球に目を付けます。国をあげて強化選手を作りあげ、現在では中国一強とも呼ばれるようになりました。
「卓球の歴史」についてよくある質問

卓球の歴史について、よくある質問をまとめて紹介します。
卓球はいつから始まったの?
19世紀、イギリスで上流階級がテニスの代わりに室内でテーブルを使って楽しんだのが、卓球の始まりです。瞬く間に、上流階級の中でブームとなりました。
卓球がオリンピック競技になったのはいつですか?
卓球がオリンピック競技になったのは、1988年のソウルオリンピックからです。1988年をスタートに、現在まで連続でオリンピック競技を継続しています。
日本に卓球が浸透し始めたのはいつですか?
1902年、東京教育大学(現・筑波大学)の教授である坪井玄道さんの手によって、少しずつ卓球が日本に伝わり始めました。
坪井玄道さん体育教育の視察でヨーロッパの各国を周り、当時ロンドンではピンポンが流行していたそうです。それを持ち帰って日本に広まったと言われています。
しかし一説には、1901年には岡山県ですでに卓球が楽しまれていたという記述もあります。語学教授として訪れていたイギリス人エドワード・ガントレットが、寄宿した三友寺で卓球を教えていたそうです。
中国が強いのはなぜですか?
アヘン戦争以降、中国は卓球を国技として強化してきました。その結果、現在でも中国選手が強いという実情が残されています。
「卓球の歴史」まとめ
卓球の歴史について解説しました。卓球はイギリスから始まり、少しずつルールや道具が変わって、誰もが気軽に楽しめるスポーツとして認識されていきました。
現在では世界中に愛される人気スポーツとなり、日本でも人気です。卓球の歴史を知ってから卓球を観戦したりプレイしてみると、感慨深いかもしれませんね。