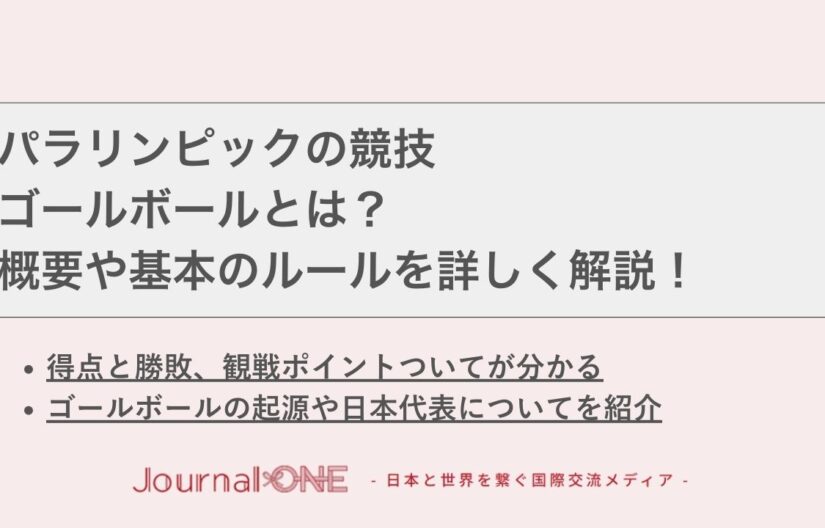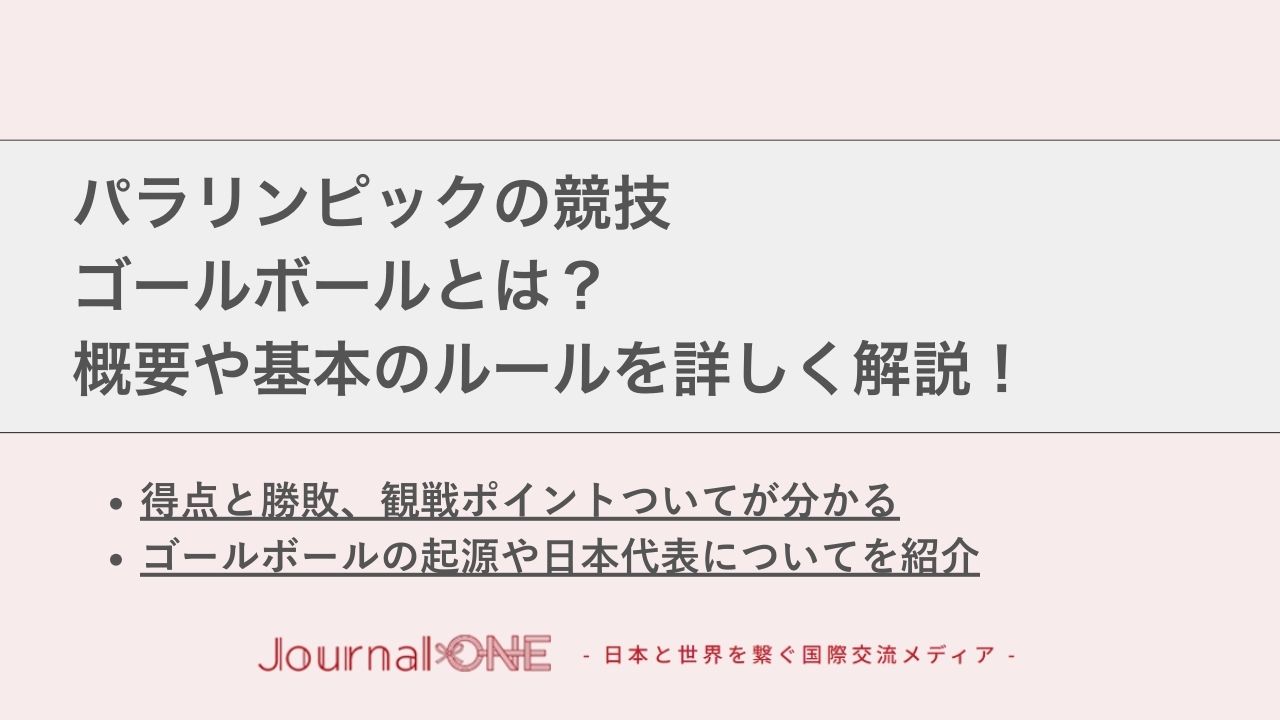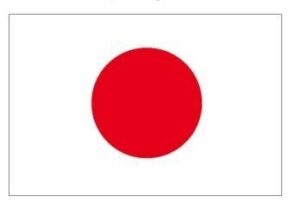音の駆け引き
ゴールボールは周りの音を聞きながらボールの位置を把握し、相手の動きを予測して動かなければいけません。
試合中は床を叩いて故意に音を出し、ボールの位置をわかりづらくする選手も多いです。投げたボールは時速60~70kmになることもあり、素早く受け止めて素早く投げ返すところも面白みを感じられます。
タイムアウト後の協力プレイ
試合中は観客や監督は音を出すことを禁じられていますが、タイムアウトが出たときは監督が相手チームの戦略を伝えられます。タイムアウト直後の試合はアドバイスを参考にできるので、試合が大きく動きやすいです。
ALSOKのスポーツ活動
ALSOKのゴールボール部は選手達が毎日トレーニングを行い、国内の競技大会や国際大会などで多くの戦績を残しています。ゴールボールは視覚以外の感覚を全集中させてボールを動かすので、相当な集中力や体力などが必要です。
ゴールボールの試合を観戦するときは、勝利を目指してひたむきに頑張る選手達に、声にならないエールを送ってあげましょう。
ゴールボールの歴史

引用:日本ゴールボール協会
ゴールボールは視覚障害がある人のための競技ですが、起源や日本に降り立ったきっかけなどはわからない人が多いです。本章ではゴールボールの起源と日本での始まりを紹介するので、ゴールボールの歴史を知りたい人は参考にしてみてください。
ゴールボールの起源
ゴールボールは終戦後の1946年に、ドイツのセット・ラインドル氏と、オーストリアのハインツ・ローレンツェン氏によって考案された競技です。当初は第二次世界大戦で視力に障害を負った軍人に対し、リハビリの効果を促進するために行われたプログラムでした。
日本での始まり
日本では1982年にデンマークから来日したクラウス・ボス氏により、東京都立文京盲学校にてゴールボールが紹介されました。当時は幅広く普及はされなかったものの、1991年の第5回フェスピック北京大会で、公式種目に認定されることが決まります。
パラリンピックでのゴールボールの日本代表は?

引用:日本ゴールボール協会
直近ではパリパラリンピック2024に、ゴールボールの試合が行われました。日本代表選手の男子部門では鳥居陽生さんや萩原直輝さん、女子部門では新井みなみさんや安室早姫さんなどが挙げられます。
どの選手も先天的に視覚障害を持っている場合や、後天的に目の難病を負った人など、さまざまなケースで視覚障害を背負った人が多くいました。しかし特別支援学校や家族の勧めがきっかけで、ゴールボールを始めるようになったそうです。
ゴールボールについてよくある質問

引用:日本ゴールボール協会
ゴールボールはパラリンピック競技として注目を集めるようになりましたが、まだ始めたばかりの人からは多くの質問が届いています。
本章ではゴールボールに向けられた質問で、とくに多い内容のものをピックアップしました。ゴールボールを始めたいと考えている人は、本章の内容から疑問点を解消してみてください。
ゴールボールはなぜ目隠しするのですか?
ゴールボールでは選手の視覚に差が出ないように、アイシェードという器具で目隠しをして試合を行います。試合は視覚が完全に閉じている状態で、頼れる情報は周りの音しかない状態です。
ゴールボールは健常者でもできますか?
ゴールボールは健常者でも、アイシェードを装着すれば視覚障害者と一緒に競技を行えます。周りの音だけでボールやほかの選手の位置を把握し、攻守の切り替えもスピーディーに行うことから試合は白熱しやすいです。
ゴールボールの選手は主にどんな障害を抱えていますか?
ゴールボールの選手は最初から視力が弱い人だけでなく、後天的に目の疾患を負って視覚障害者になるケースも多いです。後天的な病気は眼球内に悪性腫瘍ができる網膜芽細胞腫、網膜異常で発症する網膜色素変性症などが挙げられます。
ゴールボールについてまとめ

引用:日本ゴールボール協会
ゴールボールは目が不自由な人も視力に問題がない人も、アイシェードを装着すれば一緒にプレーができます。鈴が入ったボールを相手チームのゴールに目がけて転がし、足音で相手をかく乱して位置情報を誤魔化せるところも面白いです。
ゴールボールの知識やルールを押さえておけば、テレビの前でも会場で観戦しているような臨場感を味わえます。選手と観客の両方の側面から楽しめるように、ゴールボールのルールを把握しておきましょう。