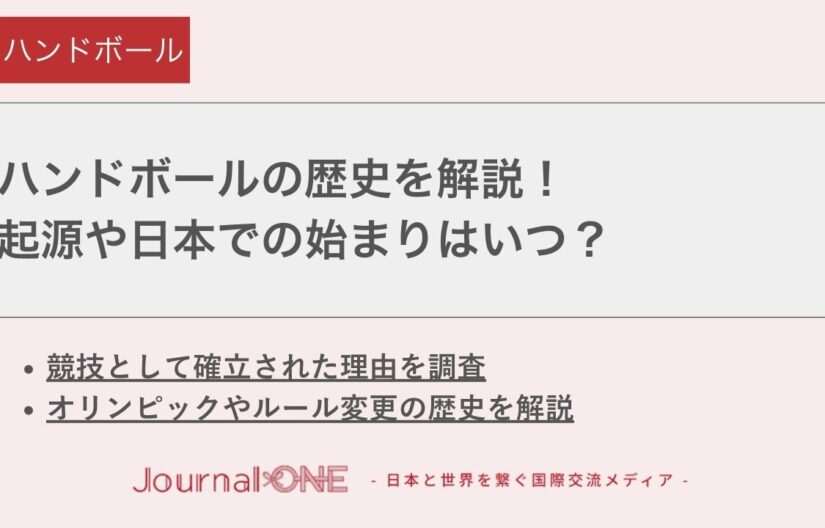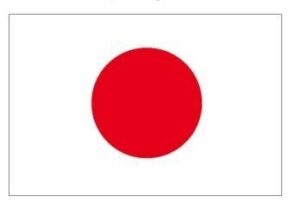華麗なパスワークと、スピーディーなフットワークに魅力されるハンドボール。TVや動画で見たハンドボールの印象は、このように華やかに映るイメージがあります。「見ていくうちに、その世界観に惹き込まれてしまう…。」と感じる方も、少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、ハンドボールの歴史について深く掘り下げてみました。ハンドボールの起源や、日本でハンドボールを始められた時期など、ハンドボールのこれまでの歴史について徹底解説します。
ハンドボールのことをもっと知りたい方や、ハンドボールについて改めて考えてみたい方は、是非こちらの記事を確認してください。
ハンドボールの歴史年表

まずは、ハンドボールの世界に記された歴史を確認してみましょう。
ハンドボールの歴史は想像よりも遥かに長いため、年表にまとめました。年表を見てみると、世界中で愛された歴史あるスポーツとして、ハンドボールの名前が刻まれていることがよく分かります。
| 時期 | 内容 |
| 紀元前5世紀頃 | ナイル川中流域にて、ハンドボールの原形がプレイされました(※壁画に痕跡有)。 |
| 紀元前7世紀頃 | ハンドボールに似ている競技が行われました。 |
| 3~4世紀頃 | ハンドボールに似ている競技「ウラニア」が行われました。 |
| 13・世紀、17世紀、18世紀 | ドイツ、フランスにて、競技が行われていたようだと伝わりました。 |
| 19世紀前半 | ドイツのコラッド・コッホ氏により、ハンドボールの原形が開発されました。 |
| 1898年 | デンマークでホルガー・ニール氏の働きにより、正式に「ハンドボール」と命名。 |
| 20世紀初頭 | デンマークの学校にて、学校体育の教材としてハンドボールが採用。 |
| 1917年 | ドイツ(ベルリン)で、第1回目の試合が開催されました。 |
| 1928年 | 国際アマチュアハンドボール連盟が正式に設立されました。 |
| 1934年 | 国際ルールが7人制となります。 |
| 1936年 | 第11回ベルリン大会より、国際オリンピック競技となります。 |
| 戦争後 | 北ヨーロッパでは7人制、東ヨーロッパでは7人制・11人制の2パターン化されますが、世界的には7人制が注目されるようになります。 |
| 1960年代 | 11人制を採用しているのは、西ドイツ・東ドイツと少数になります。 |
| 1972年 | 第20回ミュンヘン大会にて、復活します。 |
| 1976年 | 第21回モントリオール大会以降、女子競技がオリンピック競技に採用されます。 |
ハンドボールの基本ルール

ハンドボールの基本ルールを、ここで1度確認してみましょう。基本的なハンドボールのアクションは、以下の3つです。
- 跳ぶ
- 投げる
- 走る
コートプレーヤー6人、ゴールキーパー1人の7人でプレイするスタイルで、試合中であれば、選手交代は何度も行えます。コートプレイヤーとゴールキーパーのユニフォームは、デザインを変えるなどして、違いが分かるようにしなければいけません。
ユニフォームさえ交換すれば、コートプレイヤーとゴールキーパーを入れ替えることも、ルール中OKとなります。
続いて、ボールの種類をチェックしてみましょう。ボールによって重さやサイズが変わるので、年齢や性別によって使用ボールを決めることになります。
| ボールの種類 | 周囲 | 直径 | 重量 | 対象年齢・学年 |
| 0号球 | 46cm~48cm | 15cm | 255g~280g | 小学校低学年 |
| 1号球 | 49cm~51cm | 16cm | 290g~315g | 小学校男子・中学校女子 |
| 2号球 | 51.5cm~53.5cm | 17cm | 300g~325g | 中学校男子 |
| 2号球 | 54cm~56cm | 18cm | 325cm~375cm | 高校女子~一般女子 |
| 3号球 | 58cm~60cm | 19cm | 425cm~475cm | 高校男子~一般男子 |
競技時間も、年齢によって違いがあります。基本的に前半・後半と競技時間は分かれており、前半・後半共に休憩を挟みます。延長戦になった場合は、後半戦休憩の後に、更に休憩を入れることとします。詳しい競技時間は、以下の通りです。
- 小学生の場合 前半20分、休憩10分、後半20分、休憩5分
- 中学生の場合 前半25分、休憩10分、後半25分、休憩5分
- 高校生の場合 前半30分、休憩10分、後半30分、休憩5分
基本的に、ハンドボールを持てる時間はわずか3秒です。扱えるのは膝から上まで、移動できるのは3歩までです。パスをしながらプレイしますが、膝から上であれば手以外の部位を使用しても問題はありません。相手のゴールに1点入るシステムで、獲得した点数が多いチームが勝利となります。