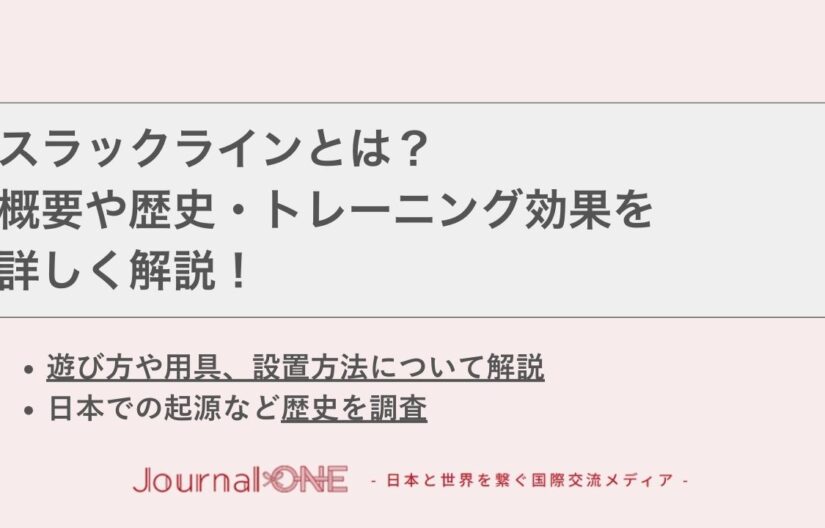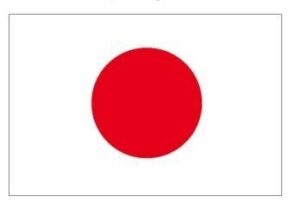スラックラインとは5cm幅のラインを二点間に張り渡し、バランスを取りながらラインの上を歩くスポーツです。年齢や性別を問わずに始められるスポーツで、低い位置に設定すれば幼稚園児からでも楽しめます。
トランポリンのようにライン上で跳ねたり、ヨガのようなポーズを取ったりなど、遊び方の幅がとても多いのも人気の理由です。最近では室内練習用のキットも次々と展開され、室内でも楽しめるようになりました。
本記事では、スラックラインの特徴や歴史について詳しく紹介します。スラックラインで得られるトレーニング効果も紹介しているので、スラックラインを始めたいと考えている人はぜひ参考にしてみてください。
スラックラインの概要・特徴

スラックラインとは2点の間にたるんだラインを張り、そのラインの上を渡り歩くスポーツです。単にラインを渡り歩くだけでなく、トランポリンの上で線の上で跳ねたり、ヨガのようにさまざまなポーズを取ったりしながら楽しめます。
概要
スラックラインは英語でSlacklineと呼びますが、英語でslack は「たるんだ」や「いい加減」という意味があります。Slacklineは日本語で「たるんだ線」という意味で、バランスを取りながら線を渡り歩かなければいけません。
遊び方
スラックラインの長さや高さに規定はありませんが、基本的には両端10m、膝くらいの高さにラインを貼るケースが多いです。線の上で歩いたり座ったりするのが難しい人は、まずはラインの上でバランスを取るところから始めましょう。
上達すればバランス感覚が研ぎ澄まされ、人間がやっているとは想像できないような技術を身に付けられます。単にアウトドアやレジャースポーツとして楽しむだけでなく、ダイエットやトレーニングとして始める人も多いです。
用具
スラックラインで必要な用具は、主に以下の3つです。
- 専用のスラックライン
- ラインや樹木を保護する養生用のツリープロテクター
- ラインが切れたときの安全対策用の補助テープ
最初のうちは幅5cm・長さ15mほどのラインを使用し、慣れるまでは怪我防止で下にマットや緩衝材などを敷いておきましょう。ツリープロテクターはスラックライン用のものがなければ、タオルで代用しても問題ありません。
スラックラインは室内でもできる?

スラックラインは公園の木に線を縛って設置しますが、条件次第では室内でも気軽に挑戦できます。地面から低くて短く設置すれば幼児でも挑戦でき、小さい頃からバランス感覚を育てやすいです。
スラックラインの設置方法

屋外でスラックラインをするときは、公園の木の間にラインを張るのが一般的です。まだ歩けない人は4~8mの短めのラインから挑戦し、高さは40cmを目安にすれば怪我のリスクが軽減されます。
設置時の注意点
ラインを縛り付ける木は直径25cm以上がおすすめで、ラインを木にくくりつけるときはツリーウェアを使用しましょう。人工物に支点を取るときは必ず、強度が十分であるかどうかを検討して設置してください。
角のある鉄柱だと角に負担がかかってしまい、厳重に要請しなければライン生地が傷んで途中で切れてしまいます。ほかには地面が柔らかい芝生や土であること、周りの人の邪魔にならない場所で行うことが大切です。
スラックラインの歴史

スラックラインは何世紀もの間、ロープやワイヤーなどを使用して行われてきたそうです。最近では高い場所にラインを張ってスリルを楽しむハイラインや、長い距離を渡るロングラインなどのジャンルが確立しました。
本章ではスラックラインの起源と、日本への起源を紹介します。スラックラインが流行したきっかけを知りたい人は、ぜひ参考にしてみましょう。
スラックラインの起源
スラックラインは1960年代にアメリカのヨセミテ渓谷にて、クライマーが暇つぶしで使い古したロープで綱渡りをしたことが起源だと言われています。1980年代始めにクライマー間で、伸縮性があるウェビングでバランスを取るという遊びが流行しました。
クライマーの間ではその遊びを「Slacklining」と呼称され、クライミング界を介して世界中に少しずつ広まっていったことがきっかけです。現在は誰もが任意の場所で練習ができるよう、スラックラインのセットが流通するようになります。
日本での起源
スラックラインが日本で流行したのは2009年で、現在は全国各地でトリックラインの大会開催されています。スラックラインのトリックラインとは、ラインの上でトランポリンのように跳ね、適当なポーズや空中回転などを行うジャンルです。
最近では日本でもスラックラインをする人が増え、手軽に楽しめるように専用の用具が普及するようになりました。スラックラインは子供から大人まで幅広く楽しめるスポーツで、体験イベントやパフォーマンスイベントなどが各地で開催されています。