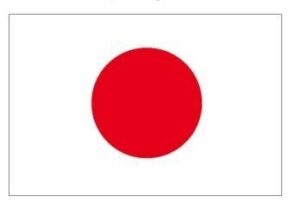観光スポット
京都 宮川町の街並み
京都五花街の一つ宮川町。京都市は東山区に位置し鴨川左岸沿に発展してきた花街である。八坂神社の祇園祭の際に神輿洗いが行われる鴨川の四条大橋下流を「宮川」と呼んでいたことが由来とも言われている。宮川町通りは清水五条から祇園四条にかけて南北700メートルに渡り伝統的な町屋や石畳の道が残る「宮川町歴史的景観保全修景地区」に指定されている。
宮川町の花街は、江戸時代から続く歌舞、音曲の芸妓や舞妓が座敷で芸を披露する場所であり、花柳界とも呼ばれる。花街では一年を通じて様々な行事が行われ、けじめや感謝の心が息づいている。神社やお寺との結びつきも強く、八坂神社の節分祭や祇園祭、平安神宮の時代祭への参加など接点が多い。特に春の「京をどり」、秋の「みずゑ會」は華やかな行事である。
宮川町の歴史は、鎌倉時代の1202年に開かれた日本最古の禅宗寺院、建仁寺の境内地を取り囲むように形成された。16世紀後半、豊臣秀吉が方広寺や伏見城を築いたことで大和大路の人の往来が増え、宮川町も発展した。寛文六年(1666)に宮川町通りが開通し、茶屋町として栄えた。宮川町のお茶屋は、芸妓、舞妓を披露する中で食事や酒を楽しむおもてなしの場である。その後、明治六年(1873)には女紅場の前身である婦女職工引立会社が設立され、明治二十九年(1896)には「京をどり」や「みずゑ會」を披露する歌舞練場が建設された。昭和二十五年(1950)には第一回「京をどり」が行われ、現在も春の年中行事として親しまれている。
スポット基本情報
食べる
買 う
観 る
泊まる
スポット情報
- 住所京都府京都市東山区宮川筋4
- TEL075-561-1151(宮川町お茶屋組合)
- アクセス京都駅 - 烏丸線 約3分 - 四条駅-徒歩約 8分
- その他

- 取材・文:
- Journal ONE( 編集部 )
このスポットの関連記事