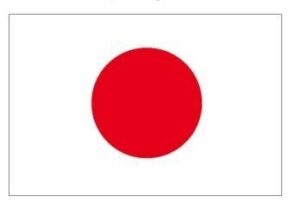向井先生から「ダルマのように丸まってみて下さい。その体勢で相手の方は四方八方から転がしてあげてください。頭を畳に着けることなくゴロゴロと前後左右に揺れることで、受身を取る感覚を掴んでもらえます。」と教わって実践。丸くなっていれば力を入れずとも、頭が畳に着くことなく、勢いを殺すことができるのですね。やってみて初めて受身を取る際の身体の使い方がわかりました。楽しみながら仕組みやコツを学ぶことで、技が自然と身に付いてくるという訳なんですね。
そして、技術以上に世界中の人々を魅了するのが、精神修養です。これについても、毎日ひとつずつ “柔道の精神” を教えていただけるのです。
例えば、大道場の壁に掲げられている “嘉納治五郎師範遺訓” に書かれている柔道の本義と修行の目的について有川先生が解説される時間もありました。「修行によって “精力善用” の原理を身につけて、知徳を磨いて人格の完成を図り、”自他共栄” を達成するために尽くすことが柔道の本質なんです。」と、外国人の参加者にも分かるように藤中先生も英語で説明されています。
この朝稽古への参加を勧めていただいた仮屋先生もそうですが、藤中先生、有川先生と皆さん英語が堪能なんです。聞くと、青年海外協力隊の一員として柔道の指導をするために仮屋先生はシリアに、藤中先生はインドネシアへの渡航歴があるなど、世界各国へ柔道指導に赴かれる先生が多いのも講道館の特徴の一つ。エジプトから参加していたムスタバさんも、熱心に嘉納師範の教えや技のかけ方を質問。気になっていた疑問が解消して、満足げな笑顔を見せていました。
人体の仕組みが分かる!丁寧な指導に感激
私たちが普段目にする柔道といえば、オリンピックなどの国際大会における日本代表の皆さんの活躍する姿です。激しいトレーニングで自らを追い込むシーンや、屈強な選手たちが懸命に戦うシーン、そして試合後に見せる感動の歓喜のシーン・・・ 皆さんが持つ “柔道のイメージ” はそういったものではないでしょうか?
例外に漏れず、私も「柔道は相当な筋力と体力を使うのでは無いか?」と思っていましたが、実は必ずしもそういった側面だけではないのです。
「お互いに正対して “組み手” をしてみましょう。」と、有川先生に教えていただき ”右組み” という体勢になります。互いに右自然体で正対して、左手で相手の右腕(袖の真ん中下あたり)を掴み、右手で相手の左の前襟を掴みます。柔道の試合で見る最初の体勢です。
「ひとりの方が、ダンスをするように好きな方向へ動いてみて下さい。そうすると、相手の方は腕を伝ってどちらに動こうとしているかが分かると思います。」との説明で、ペアの加賀さんが動くと・・・ 確かに!どちらに動こうとしているかが、袖や襟から伝わってきます!
「常に正対するように、相手の方は動きを察知した方向に合わせて動いてみて下さい。足元を見ないで正面を向いて相手の身体全体をぼんやり見るようにすると様になりますよ。」と藤中先生にポイントも教えていただき、さながら “柔道の組み手ダンス” が始まりました。
「足を交差させないよう、摺り足で動いてみて下さい。そう!すっかり経験者の組み手になりましたよ。」と有川先生に褒めていただき、最初は遠慮がちに動いていた私たちも楽しくなり「動きが予測できますよ!」「腕がセンサーになって、身体が勝手に反応しますね!」と、感心しながら稽古に熱中しました。
「組み手をする際、両手首を絞ってみて下さい。それだけで、力が無い人でも相手の動きを制限することが出来ますよ。」と、向井先生に教わった通りにすると・・・ 腕や肩に力を入れなくても簡単に相手の動く範囲を狭めることに成功しました!これならば、筋力の無い私たちでもしっかり相手と組み合うことができる訳ですね。
向井先生の「人間の身体は、何度前に傾くと倒れるか知っていますか?」という問いかけに、「え?そんなこと考えてもみなかった・・・」と頭を捻る私たちに、「柔道だから、10度(じゅうど)です(笑)!」と、ユーモアを交えて人体の仕組みを教えていただくシーンもありました。
相手を安定した立て膝の状態にして組んで、前にゆっくりと10度倒すと・・・本当です!前に倒れそうになって、思わず片方の膝を前に擦り出してしまいます。
「この相手が “崩れた” 状態の時に、前に出そうとする膝に足を投げ出すと・・・引っかかって倒れますよね。これが柔道の相手を崩して技を掛ける仕組みなのです。」と向井先生に技を掛けるタイミングを教わり、実演に通りにやってみると、勝手に相手が転がっていきます。人体の仕組みを分かりやすく紐解きながら柔道技に繋げていくことで、”柔よく剛を制す” と言われる意味がストンと腹落ちしていきます。
「因みに、この動きを立った状態でできるようになると、“膝車” という投技の一つになります。皆さん、既に一つの技を習得しましたね。」と、向井先生に褒めていただき益々やる気がみなぎってきました。先生方は、生徒を乗せるのがとても上手い(笑)!