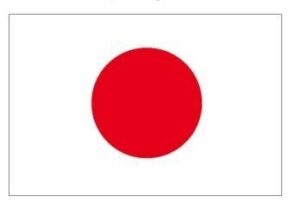教わる人の経験値や、反応を見ながら時にユーモアを交えて様々な視点から指導していただくことで、今まで抱いていた『柔道をするって大変なんだろうなぁ』というイメージが払拭され、『あぁ、柔道って人体の理にかなった誰でも気軽に出来る運動なんだ!』ということに気付かされます。
柔道家になった気分で!先生との交流
柔道の技の種類は、投技68本、固技32本の計100本! 投技の実践は、やはり受身がしっかりできるようにならないと危険ということが分かりましたので、「7日間の稽古では、技を習得するまでは到達しないのだろうなぁ・・・」と思っていました。
すると、「それでは、ひとつの技を実際にかけてみましょう。柔道でよく使う固技のひとつ、袈裟固(けさがため)をやってみます。」と有川先生に提案され、私たちに笑顔がこぼれます。袈裟固は32本の固技の中にある抑込技の一つで、相手をあおむけにして概ね向かい合い、首と片腕を制して抑え込む技です。足を大きく前後に開いてバランスをとり、脇に挟んだ相手の腕をしっかりとロック。相手がブリッジをしたり、足を自分の足に絡めて逃れようとするのを持ちこたえる必要があるため、しっかりと相手に上半身を密着させながら足の動きにも注意しなければなりません。
「それではお互いに技をかけ、それから逃れる練習をしましょう。」と、有川先生と藤中先生の実践を見つめます。ズサササ、ザザッと、畳と柔道衣が擦れる音は逃れようとする藤中先生の動き。これ実際にやってみますと、畳と柔道衣が密着してなかなか動くことができないのです・・・ 「できるだけ畳と柔道衣の接地面を少なくすることで、摩擦の抵抗力を弱めて動くことがポイントです。」と、物理学を鑑みた動きのポイントを向井先生が教えてくれます。
加賀さんと組んで3~4回攻守を入れ替えます。互いに逃れたり抑え込んだりと集中して取り組んでいますと、身体全体が熱くなりじんわりと汗が出て息が上がってきます。「相手との距離、また畳との距離といった “非日常的な近さ” が自分にとってまさに異世界でした。知らない土地へ旅すること、言葉の通じない海外へ行くことも異世界ですが、日常生活の中で “いつもより一歩近づいてみる” ことで覗くことのできる異世界があることを教えてくれた今回の講道館朝稽古には感謝ですね。」と加賀さんが話していたとおり、時間を忘れて異世界を楽しみました。
有川先生にお願いして、私と加賀さんがそれぞれ受、取として袈裟固を体験させていただきます。先ずは加賀さんが有川先生の技から逃れる場面です。フン!フン!と加賀さんが力を入れますが、全く動きません・・・ 「ここまで決まると有段者でも逃れることは難しいのですが、身体を密着させてスペースを空けないことで、力を入れなくても相手は動けなくなるのです。」と、抑え込むポイントを教えてくれる有川先生。
今度は私が有川先生に袈裟固をかける場面です。教わった通り、有川先生に体を預けて隙間無く抑え込んでいたと思っていましたが、スッっと有川先生が動いた瞬間にあっという間に技が解け、今度は私が袈裟固をかけられた状態になってしまいました!「脇に少しスペースがあったので、そこから一気に腕を抜くことができましたよ。」と涼しい顔で抑え込む有川先生。
腕力で相手を抑えつけないと言いますが、一体有川先生はどこに力を入れるのですか?と尋ねると、「あばら骨の下辺りにある筋肉を締める位ですかね。」と答えた瞬間、一気に身体が抑えつけられて息ができません・・・ そもそも、その部位の筋肉はこんなに収縮するのか? その部位の筋肉を強めるだけで息もできなくなるのか?と苦しみながらも感心して聞き入ってしまいました。
更に、「折角なので、絞め技も体験してみましょうか?」とニッコリ微笑む有川先生。絞技とは抑込技、関節技と合わせた、固技32本に分類される技。並十字絞、逆十字絞、片十字絞、裸絞、送襟絞、片羽絞、胴絞、袖車絞、片手絞、両手絞、突込絞、三角絞の12種類があり、素人でも分かる “必殺の強力技” です!
「実際にかける寸前までやってみます。本当にかかってしまうと、とても苦しいので(笑)。」と話す有川先生の笑顔に、一同沈黙・・・ その沈黙を破り、最初に臨んだのは加賀さん。「しない後悔より、して後悔。」と前向きな加賀さんの頸動脈(けいどうみゃく)に有川先生の袖が触れた瞬間、「ウッ!」という声と共に顔が真っ赤になってしまった加賀さん。もちろん、私も次に実演していただきましたが、手を添えられただけで息苦しくなるんです!
この体験には続きがあります。それは、落ちた後の正しい活法。絞められて落ちるのは、頚動脈洞反射によるもの。頚動脈の血流が遮断されると迷走神経が過剰な反射を起こし、心臓にその情報が伝わり徐脈(拍動が異常に遅くなる)となります。すると、血圧が低下して脳幹へ行く血液が少なくなり脳幹での酸素量減少で失神状態に陥るという仕組みです。