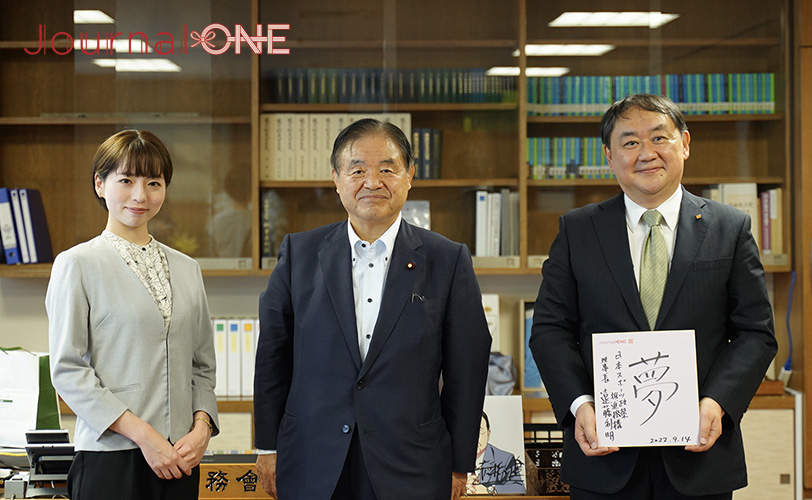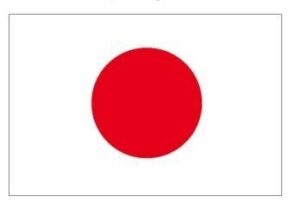国際化のスタンダードが変わる? ラグビーの国際活動
-今年3月に開催された野球の世界大会WBCでは、ラグビーの代表選出方式を参考に、国籍を有さない選手も参加が可能となり、盛り上がりました。こう言った代表選出の仕組みを早くから取り入れているラグビーは、日本でプレーする外国籍選手が多い理由の一つでもあると思います。
高校生からリーグワンまで様々な世代の選手が、様々な国から来日してラグビーをしています。彼らが日本人選手や関係者、ファンと交流する光景は、日本国内における国際化のスタンダードになっていくのではと期待しています。
ラグビーならではの特徴的な国際化に対応するため、ラグビー協会が進めている国際活動について教えてください。-
ラグビー日本代表は、早くから日本の世論に “多様性” を考えるきっかけを与えていたと思います。1999年のワールドカップ日本代表では、初の外国人主将としてAndrew McCormick(アンドリュー・マコーミック)選手を指名しました。この時、マスコミは「何で外国人を日本代表のキャプテンにするんだ?」といった報道が多く見られました。
しかし、今の日本代表選手は40%が外国出身選手です。2015年のワールドカップでリーチ マイケル選手がキャプテンとなった時には、もうその様な報道はありませんでした。
リーチは、ワールドカップ前の宮崎合宿の合間に “君が代” の歌詞にある「さざれ石」がある日向市の大御神社(おおみじんじゃ)まで出向き、同じ代表の外国人選手に「これが君が代に出てくる “さざれ石” だ。」と説明していました。こういった、日本を理解しようとする選手を日本代表に選んできたことが、国内の理解を生んだのだと思います。また、彼らは日本人選手と同様に厳しい練習に取り組みます。こういった日本のマインドに合った選手だけを選ぶことが必要だとエディは常々話していました。
また、日本代表に限らず、日本におけるプレーの機会を広げてきたことも国際化への対応として大きな役割を果たしたと思います。南半球のトンガ、フィジー、サモアといったラグビー強豪国の学生たちはいままで、ニュージーランドに多く留学していました。しかし、ニュージーランドに留学してラグビーをしていてもなかなかプロにはなれません。こういった選手たちを日本に呼びますと、親御さんはとても喜んでくれるのです。高校から日本に留学すれば、大学に進学でき、社会人で社員として給料を貰いながらラグビーができる訳ですから。
女子ラグビーにも期待
-ラグビー界の大きなニュースが5月にもうひとつありました。ラグビーワールドカップ2023の開催に先立ち、5月14日までフランス・トゥールーズ大会で開催されていた、世界最高峰の “ワールドラグビー・セブンズシリーズ”。ラグビー女子7人制日本代表 “サクラセブンズ” が見事に5位入賞を果たしました。東京2020大会(12チーム中で12位)から、短期間で大きく躍進しましたね。-
男子15人制ラグビーと同じく、7人制ラグビー、特に女性活躍の視点から “サクラセブンズ” にはとても力を入れています。女性のラグビーファンを増やすためにも、女子ラグビーの実力、人気、競技人口の拡大は大事です。ラグビー協会でも4割を占めている女性理事や、女性職員の意見も聞きながら、“サクラフィフティーン” ”サクラセブンズ” の人気を高めていきたいと考えています。
オリンピックにおいてのラグビー競技は7人制が合っています。オリンピックの開催期間は3週間弱、一方で15人制のラグビーは1週間に1試合できるペースですので、15人制は日程の都合上でどうしてもオリンピックと合わないのです。それに対し、7人制のラグビーは男女それぞれで競技ができますし、試合日程も問題が無い。
また、2050年までにラグビーワールドカップの日本開催を誘致していますが、これが実現すれば女子15人制のワールドカップも2年後に日本で開催されることになります。そのためにも、何としても日本開催を実現したい。実現に向けての活動がラグビー協会会長の私の使命だと考えています。オリンピック、そしてラグビーワールドカップという大きな舞台で躍動する女子ラグビー を是非、皆さんその目で見ていただきたいですね。
日本の未来を創るラグビー
-地域課題の解決策としてスポーツの力を活用しようという声が高まっています。特に、少子高齢化に伴い地域スポーツの未来をどうするかが議論されています。日本全国にその人気が益々広がっていくラグビーが、地域スポーツの未来にどういった貢献ができるとお考えでしょうか?-
スポーツ庁は、少子高齢化、地域活性化、地域の部活動問題などの様々な課題解決にスポーツを活用していく政策を打ち出していますので、これに連携しています。また地方自治体、例えば高校ラグビーの聖地・花園ラグビー場がある東大阪市でも、スポーツをするだけでなく見る機会を増やそうと、70歳以上の市民に無料チケットを配布してラグビーの魅力を体験してもらう取り組みをしています。お孫さんを連れて観戦されるケースもあるので、子どもたちがラグビーに触れる良い機会にもなります。